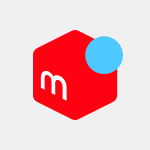①鑑賞現代詩Ⅰ-明治 吉田精一 筑摩書房 1968年新版第2刷
明治15年に出た『新体詩抄』を土台として日本の近代詩は急速に発展し、透谷・藤村・泣菫・有朋の名作を生み、明治末期には白秋・杢太郎・露風の華麗な花を咲かせた。この巻においては、多くの名作をたどりながらその経過を鮮やかに描いている。
吉田精一(1908-1984)は日本の国文学者。1940年(昭和15年)の処女作『近代日本浪漫主義研究』で頭角を現し、1951年(昭和26年)より日本近代文学会の中心となる。文献学批判の立場から、独自の美学的根拠にたつ実証研究を確立したが、芥川龍之介、永井荷風、谷崎潤一郎といった現代作家を研究対象とすることは当時のアカデミズムでは異例のことであった。
明治詩の流れ/北村透谷/国木田独歩/島崎藤村/土井晩翠/与謝野鉄幹/伊良子清白/横瀬夜雨/与謝野晶子/薄田泣菫/蒲原有明/児玉花外/河合酔茗/石川啄木/森鷗外/北原白秋/木下杢太郎/三木露風/訳詩
全体的にヨゴレがありますが、本文はおおむねきれいな状態です。
②鑑賞現代詩Ⅱ-大正 伊藤信吉 筑摩書房 1968年新版第2刷
明治末の白・露時代に育まれた光太郎・春夫・犀星・朔太郎等は大正に入ってみごとな結実を見せ、日本語の美しさを見せるとともに思想的な深さをも加えていった。賢治・重吉・米次郎・耿之介、そして恭次郎をはじめとするプロレタリア詩への流れを、名詩を追いながらたどる。
伊藤信吉(1906-2002)は詩人、近代文学研究者。初めアナキズムの影響を強く受けたが、のちマルクス主義に移り、1928年(昭和3年)に上京し「ナップ」に加盟した。萩原朔太郎、室生犀星、草野心平の知遇を得て、詩人として活動を開始する。しかし、最初の詩集『故郷』刊行後に詩作を止め、詩人論や現代詩鑑賞などの評論著述に専念、萩原や室生などの詩人全集の編集に携わった。
大正期の詩と詩人/高村光太郎/武者小路実篤/佐藤春夫/山村暮鳥/室生犀星/萩原朔太郎/堀口大学/西城八十/千家元麿/百田宗次/尾崎喜八/宮沢賢治/八木重吉/共感と愛誦の詩/訳詩
全体的にヨゴレがありますが、本文はおおむねきれいな状態です。