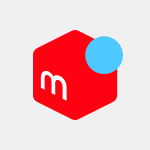祖父が集めていたものです。
鳴子こけし特徴の首を捻るとキュキュて音がします。
頭部にワレがありますが広がったり裂けたりはしないと思います。
岡崎斉司(おかざきせいし:1926~2002)
系統:鳴子系
師匠:岡崎斉
弟子:岡崎斉一/早坂彰康
〔人物〕 大正15年2月5日、鳴子湯元岡崎斉・ふみよの長男に生まる。昭和15年3月15歳で鳴子高等小学校卒業後、父斉について木地を修業した。こけしは小学校時代より描彩を始めた。深沢要は〈こけしの追求〉に、「斉の長男斉司は昭和14年の夏、疋田重安が挽き残したこけしの木地に描彩の稽古をしたのが始で、最近は木地描彩共に自分のものを作っている。寡作者と云われている斉と息子のこけしが仲良く店の棚に並んでいるのは微笑ましい。(昭和16年)」と書いている。
昭和15年7月に鳴子で開催された東京こけし会のこけし鳴子大会には最年少で参加するなど、工人と蒐集家つなぐ役割も積極的に果たしていた。
昭和19年9月志願兵として海軍に従事、昭和20年8月30日まで勤めた。
戦後長い間、湯元の坂を上る左側の店で父斉と共にこけしを作り続けた。弟子には早坂彰康・長男の岡崎斉一がいる。
戦前の川口貫一郎氏編集の東京こけし会機関紙〈こけし〉で名前が知られたが、写真紹介は〈こけし・人・風土〉が最初であろう。
戦後のこけしブームの時には、桜井昭二、大沼秀雄、遊佐福寿、高橋正吾とともに若手五人衆と呼ばれたが、その最年長であり、 各地のこけし会などにも参加して活躍した。昭和40年より5年聞鳴子木地玩具協同組合理事長を勤め、その後も引き続き理事として後進の世話をした。
平成14年8月5日没、行年77歳。
350mlノンアル缶は大きさの比較の目安で商品には含まれません。