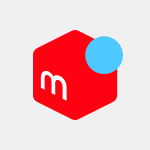《最高品質販売》
脚付碁盤
[アシ・ヘソ あります]
囲碁 Go Aller Andare 去
囲碁盤の四隅には脚(あし)をはめこむ穴があります。また盤の中央には四角のくぼみがあります。
盤の脚(あし)高級な盤には、凝ったデザインの脚がついています。江戸時代には、こうしたデザインの脚が作られるようになったようです。これは「梔子」(くちなし)の実をかたどったものです。なぜ梔子なのか。それは「『口なし』という言葉に由来し、その通り、助言をいましめる意味がある」という伝説です。盤の裏のくぼみに関して、このくぼみは一般的には「へそ」、時には「血溜まり」(ちだまり)と呼ばれます。「血溜まり」とは物騒な言い方ですよねこれは「助言をしたものの首をはね、ここに据えたことに由来する」ということの様です「江戸時代の田宮仲宣という戯作者が1801年、『橘庵漫筆』という著作に書いています。最も古い文献上の資料の『血溜』(ちだまり)の話に関しては田宮仲宣は『琅邪代酔編』に書いています。図書館で学びましょう。碁盤盤のへそには実用的な意味があります。小松碁盤店の小松武樹さんは、「助言をした人の首を斬って載せた時の血溜りという人もおりますが、専門的立場からいいますと裏は表よりも空気の当たる率が少なく、盤が狂いやすくなりますので、裏にヘソを彫り空気のふれる面を多くして狂いを防いだのです。またヘソは碁石や駒を打ったときの音をよくするためでもあると考えられます。」
♯囲碁
♯脚付き
♯天然木製
♯樹齢○年
☆フィリップアンダーソン
ノーベル物理学賞受賞者
日本棋院 名誉三段「自分はノーベル賞受賞者としては川端康成氏についで二番目に碁が強い」と語った。
☆ 山中伸弥
高校のときに始めて、いちど辞めたが2016年末からまた始める。
詰碁を毎日数問解いている。
☆ 堀 義人 @YoshitoHori
グロービス経営大学院 学長
グロービス・キャピタル 代表パートナー
『今、囲碁が流行り始めている。』と語った。
☆織田信長 本能寺の変の前日1582年6月20日の夜、本因坊算砂(ほんいんぼう・さんさ)と、それに勝るとも劣らない本能寺の僧侶である利玄(りげん)が本能寺で対局していた。織田信長がこの対局をかぶりついて観戦していて「三コウ」という珍しい形が出現。
ランク···特上
販売種別···単品