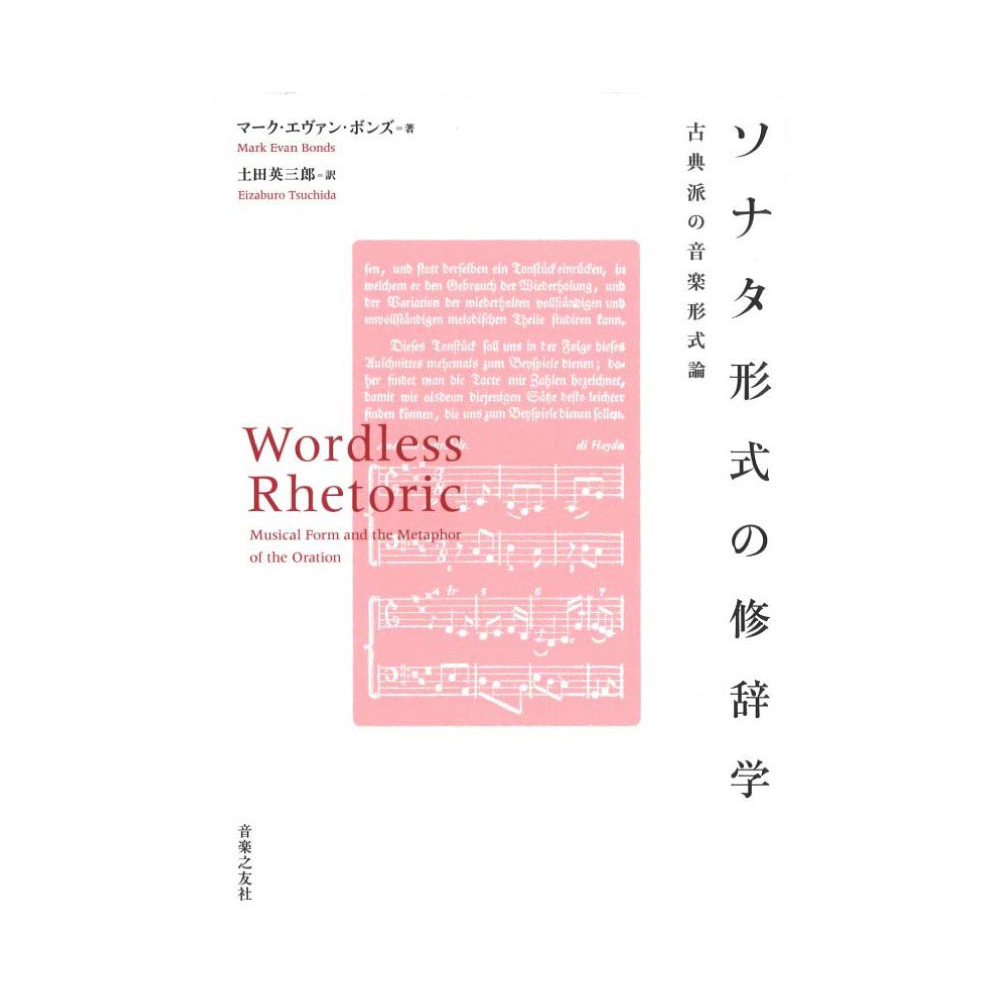1 / 1
Please read the item description carefully as the item photos may not match the actual product.

Price
¥ 5,060
Quantity

1
Japan Domestic Shipping
¥0
Seller
Sale
2.14-2.14, Mercari 7% + ¥1000 OFF!
2.13-2.19, TCG Sites 5% off!
2.12-2.16, Rakuma 7% off & Rakuten 5% off!
2.11-2.14, Amazon + Surugaya¥1,000 OFF!
2.01-2.28, One "0 Proxy Fee" coupon daily!

This seller's other items
More
Copyright © 2015-2025 doorzo.com, All Rights Reserved
Shipping Calculator
New Users‘ Guide
FAQ
Customer Ticket
Customer Support