Please read the item description carefully as the item photos may not match the actual product. View original page
特別陳列 京都府の古瓦 1973.7.20-8.31 丹後郷土資料館 考古学
¥ 4,100
( ≈ -- )


Please read the item description carefully as the item photos may not match the actual product. View original page



¥ 4,100
( ≈ -- )
This seller's other items
More
限界の空を奔る彗星蘭 いぬきら 狗神煌 サクラノ詩 サクラノ刻 本間心鈴
¥ 4,700
( ≈ -- )
【箱不要の場合は値引きします】★未使用品★素晴らしき日々 不連続存在 ケロQ
¥ 11,000
( ≈ -- )
C104 夏コミケ 向日葵の教会と長い夏休み 夏咲詠 アクリルスタンド アクスタ
¥ 1,390
( ≈ -- )
向日葵の教会と長い夏休み 鮎ヶ瀬月子& 夏咲詠 アクリルスタンド アクスタ
¥ 2,700
( ≈ -- )
特別陳列 京都府の古瓦 1973.7.20-8.31 丹後郷土資料館 考古学
¥ 4,100
( ≈ -- )
【未使用品】ケロQ 素晴らしき日々 -不連続存在- げっちゅ屋特典 テレカ テレホンカード 水上由岐 かわしまりの
¥ 4,200
( ≈ -- )Related Items

森本六爾関係資料集 II
¥ 2,500
( ≈ -- )
特別陳列 京都府の古瓦 1973.7.20-8.31 丹後郷土資料館 考古学
¥ 4,100
( ≈ -- )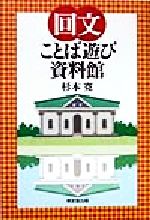
回文ことば遊び資料館
¥ 990
( ≈ -- )
遺跡を探る 飛鳥資料館 2001年 考古学
¥ 327
¥ 327

▲01)【同梱不可】【除籍本】山口大学 遺跡・文化財など/年報まとめ売り18冊セット/埋蔵文化財資料館/構内遺跡調査研究/考古学/B
¥ 2,860
( ≈ -- )
9T★/1/遺跡・考古学関連本まとめて約30冊セット 薄い本あり/音の考古学 古代の響き/銅鐸 辰馬考古資料館/古代研究/月刊文化財ほか
¥ 0
¥ 3,230

O-ш/ 飛鳥の考古学 飛鳥の古墳調査最前線 飛鳥資料館カタログ第33冊 平成28年1月29日発行 奈良文化財研究所
¥ 0
¥ 511

匿名配送/ビジュアル博物館 No.56 考古学/カバーなし/写真図鑑
¥ 500
( ≈ -- )
河内の中世考古学展図録
¥ 1,000
( ≈ -- )
大宰府史跡 昭和54年度発掘調査概報 九州歴史資料館 考古学
¥ 327
¥ 327

図録『庄内川流域の古代文化』東濃西部歴史民俗資料館 瑞浪陶磁資料館/平成2年 埋蔵文化財 考古学 郷土史
¥ 0
¥ 1,000

NB041/ 「仏像・仏具・考古資料」 服部和彦氏寄贈資料図録Ⅲ 國學院大學考古学資料館 /木造仏 厨子 泥仏 石仏 神像 狛犬 道祖神
¥ 0
¥ 3,800

現代博物館学入門 /ミネルヴァ書房/栗田秀法(単行本)
¥ 1,926
( ≈ -- )
東北歴史資料館 研究紀要 第5巻 昭和54年 考古学
¥ 327
¥ 327

東北歴史資料館 研究紀要 第6巻 昭和55年 考古学
¥ 327
¥ 327

図録 カタログ 西南四国の中世社会と公家 考古学 中世史 一条家 西園寺 九条
¥ 2,860
( ≈ -- )
大宰府史跡 平成9年度発掘調査概報 九州歴史資料館 考古学
¥ 327
¥ 327

L-ш/ 國學院大學 考古学資料館紀要 開館七十周年記念 第15輯 平成11年3月31日発行 國學院大學考古学資料館
¥ 0
¥ 690

▲01)【同梱不可】【除籍本】山口大学 遺跡・文化財など/年報まとめ売り18冊セット/埋蔵文化財資料館/構内遺跡調査研究/考古学/B
¥ 0
¥ 2,200

特別陳列 京都府の古瓦 1973.7.20-8.31 丹後郷土資料館 考古学
¥ 4,100
¥ 4,100

《希少 貴重 播磨大中遺跡の研究 播磨町郷土資料館》播磨町教育委員会 平成2年 考古学
¥ 1,805
¥ 1,805

図録 カタログ 文字のささやき 考古学 銅鏡 木簡 墨書土器 須恵器 古瓦
¥ 1,650
( ≈ -- )
『國學院大學 考古学資料館紀要』第17輯/國學院大學考古学資料館/平成13年 埋蔵文化財 考古学 郷土史
¥ 0
¥ 1,000

博物館資料論 改訂新版/放送大学教育振興会/佐々木利和(単行本)
¥ 1,163
( ≈ -- )
京都秀吉の時代 つちの中から
¥ 1,000
( ≈ -- )
資料 国士舘大学 考古学資料館要覧 1990年 石器 土器
¥ 500
¥ 500

『千葉県立房総風土記の丘 資料館図録』昭和51年 遺跡 古代 考古学 郷土資料 民俗学
¥ 0
¥ 500

★ 【図録 星々と日月の考古学 飛鳥資料館 2011年】192-02412
¥ 0
¥ 1,320

『播磨大中遺跡の研究』播磨町教育委員会/播磨町郷土資料館/1990年/函スレキズ 兵庫県加古郡播磨町 埋蔵文化財 考古学 郷土史
¥ 0
¥ 1,000

図録 カタログ 京都平野と豊国の古代 考古学 豊前 古墳 前方後円墳 埴輪 勾玉
¥ 1,980
( ≈ -- )
図録『東海の形象はにわ展』東濃西部歴史民俗資料館 瑞浪陶磁資料館/昭和62年 埋蔵文化財 考古学 郷土史
¥ 0
¥ 1,000

『奈良国立文化財研究所 飛鳥資料館案内』1975年 埋蔵文化財 考古学 郷土史
¥ 0
¥ 1,000

〈図録〉 『開館5周年記念特別展 乙訓の古墳文化』 向日市文化資料館 ※仏獣同笵鏡、埴輪、等。52点の図版収録。
¥ 1,000
( ≈ -- )
K-3643■国学院大学 考古学資料館要覧 1982■新収蔵資料■国学院大学考古学資料館■昭和57年11月4日発行
¥ 500
¥ 500

大宰府古文化論叢 上下巻セット 九州歴史資料館開館十周年記念 1983年 清川弘文館●定価20000円/福岡県太宰府市/伊都国の考古学●A5618-8
¥ 0
¥ 1,980

考古学入門 /東京大学出版会/鈴木公雄(単行本(ソフトカバー))
¥ 360
( ≈ -- )
考古学ライブラリー20 博物館・資料館案内2 シミ有/OAQ
¥ 1,800
¥ 488

図録 カタログ 船原古墳とかがやく馬具の精華 考古学 古墳時代 前方後円墳 埴輪
¥ 2,750
( ≈ -- )
考古学ライブラリー7 博物館・資料館案内1 シミ有/OAQ
¥ 1,800
¥ 488

『水無月山遺跡 発掘調査報告書』京都府立丹後郷土資料館/1980年 埋蔵文化財 考古学 郷土史
¥ 0
¥ 1,000

【レア・朝日新聞・雑誌】 戦後50年 古代史発掘 総まくり アサヒグラフ別冊
¥ 1,500
( ≈ -- )
図録『三河の銅鐸』蒲郡市郷土資料館/昭和56年 埋蔵文化財 考古学 郷土史
¥ 0
¥ 1,000

資料 国学院大学 考古学資料館紀要 第6集/姶良Tn火山灰降下期における黒曜石石器群 記号としての土器
¥ 1,000
¥ 1,000

資料 国学院大学 考古学資料館紀要 第7集 武蔵台Xb文化層の系譜 多縄文系土器 浮線文系土器
¥ 0
¥ 1,000

黒塚古墳のすべて 橿原考古学研究所附属博物館特別展の図録
¥ 1,800
( ≈ -- )
『六郷山寺院遺構確認調査報告書VI』大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館/1998年 埋蔵文化財 考古学 郷土史
¥ 0
¥ 1,000

図録『古代の塩作りと海』和歌山県立紀伊風土記の丘資料館/1995年 郷土史 紀伊半島 製塩土器 埋蔵文化財 製塩遺跡 遺物 考古学
¥ 0
¥ 1,000

財団法人辰馬考古資料館「展観の栞」まとめて8冊一括/昭和53年度〜平成13年度 兵庫県西宮市 銅鐸 古鏡 埋蔵文化財 考古学 郷土史
¥ 0
¥ 1,000

考古学研究法 遺跡・遺構・遺物の見方から歴史叙述まで/新泉社/勅使河原彰(大型本)
¥ 2,563
( ≈ -- )
絶版◆◆週刊日本の歴史87 維新と明治の新政◆◆大政奉還と討幕の密勅 徳川慶喜 戊辰戦争と版籍奉還 軍隊 西洋文明 廃藩置県 西南戦争 即決
¥ 1,350
( ≈ -- )
人■ 器財はにわの世界 関東の器財埴輪 第12回企画展 栃木県立しもつけ風土記の丘資料館編 考古学 埴輪
¥ 0
¥ 1,000

『名古屋の縄文時代 資料集』名古屋市見晴台考古資料館/1993年 遺跡発掘調査 埋蔵文化財 考古学
¥ 0
¥ 1,000

図録「葛城氏の実像 葛城の首長とその集落」橿原考古学研究所附属博物館
¥ 4,880
( ≈ -- )
262129京都丹後 「竹野川の遺跡 私たちの考古学Ⅲ」京都府立丹後郷土資料館 郷土史 B5 121478
¥ 0
¥ 1,800

展覧会カタログ 飛鳥資料館「飛鳥の考古学2021」
¥ 0
¥ 500

『大垣の古墳』大垣市歴史民俗資料館/1987年 岐阜県大垣市 埋蔵文化財 考古学 郷土史
¥ 0
¥ 1,000

図録『石棚と石梁 岩橋干塚の横穴式石室をさぐる』和歌山県立紀伊風土記の丘資料館/1996年 郷土史 紀伊半島 埋蔵文化財 古墳 考古学
¥ 0
¥ 1,000

絶版◆◆週刊日本の歴史 戦国大名◆◆群雄割拠 領国支配―富国強兵☆尼子経久・長宗我部元親・斎藤道三・武田信玄・上杉謙信・龍造寺隆信
¥ 1,350
( ≈ -- )
人■ 飛鳥池遺跡 <飛鳥資料館図録 第36冊> 関西プロセス 奈良国立文化財研究所飛鳥資料館 著 考古学 発掘調査
¥ 0
¥ 1,000

特別陳列 京都府の古瓦 1973.7.20-8.31 丹後郷土資料館 考古学
¥ 4,100
( ≈ -- )
『瑞浪陶磁資料館研究紀要』第4号/東濃西部歴史民俗資料館 瑞浪陶磁資料館/1988年 岐阜県瑞浪市 埋蔵文化財 考古学 郷土史
¥ 0
¥ 1,000

考古資料大観 第5巻/小学館(大型本)
¥ 145,176
( ≈ -- )
『六郷山寺院遺構確認調査報告書V』大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館/1997年 国東半島 埋蔵文化財 考古学 郷土史
¥ 0
¥ 1,000

資料 国学院大学 考古学資料館要覧 1981年 祭礼遺物
¥ 1,000
¥ 1,000

『おおいたの歴史と文化 常設展示の案内』大分市歴史資料館/昭和63年 大分県 埋蔵文化財 考古学 郷土史
¥ 0
¥ 1,000

◎3冊 國華 第1508/1509/1510号 弥生土器/花鳥図屏風/明清絵画の新たな視点 等
¥ 4,500
( ≈ -- )
【美品】展覧会カタログ 飛鳥資料館「飛鳥の考古学2022」
¥ 0
¥ 500

【住む。 2024年11月号】泰文館
¥ 1,200
( ≈ -- )
人■ 律令国家の地方官衙 古代の役所2 <企画展> 栃木県立しもつけ風土記の丘資料館編 考古学
¥ 0
¥ 1,500

『大分県内 石造文化財の現状と課題 保存のための基礎調査 概報』大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館/平成6年 考古学 郷土史
¥ 0
¥ 1,000

図録『古代狭田王国の興亡』鹿島町立歴史民俗資料館/1989年 島根県 郷土史 埋蔵文化財 遺跡 遺物 考古学
¥ 0
¥ 1,000

博物館・資料館案内Ⅱ/考古学ライブラリー20■昭和59年/初版
¥ 0
¥ 200

『見晴台遺跡 遺構編 発掘調査報告書』名古屋市見晴台考古資料館/1993年/函スレキズ 郷土史 考古学 埋蔵文化財
¥ 0
¥ 1,000

図録『昔のくらしと遺跡 岩橋千塚の時代』紀伊風土記の丘資料館/昭和59年 郷土史 紀伊半島 埋蔵文化財 遺跡 遺物 古墳 考古学
¥ 0
¥ 1,000

図録『原始・古代の紀伊国』和歌山県立紀伊風土記の丘資料館 郷土史 紀伊半島 埋蔵文化財 遺跡 遺物 古墳 考古学
¥ 0
¥ 1,000

Copyright © 2015-2025 doorzo.com, All Rights Reserved